子供の反抗期と発達障害

反抗期はそこそこ強めだったひだち教室長の安藤です。
多くの人に反抗期があります。
反抗期で今までの親子関係が崩れ、親は悩みます。
でも、子供の成長に必要な時期でもあります。
当然、発達障害のある子供にも反抗期はあります。
単純に反抗期だから一時的なものと考え、放ったらかしにされたという話もよく聞きます。
その結果、心を病んだり、暴力行為を及ぼすといった二次障害を発症するなんてこともあります。
反抗期故の反発と障害の特性からくる反発、その両方による反発がありますが、その見極めは難しい。
今回は、反抗期と発達障害についてお話したいと思います。
反抗期は成長に必要

反抗期は一般的に、
「子供が人の意見や指示に反抗することが増える時期」を意味しています。
反抗期は2回あります。
第一次反抗期は、自我意識が芽生える2~3歳。
第二次反抗期は、自我感情が強く意識され、それが反抗として現れる青年期初期。
幼児の反抗期

2~3歳の第一次反抗期はいわゆるイヤイヤ期というもの。
保育所勤めの時もよく見かけました。
何かをやってあげようとすると「イヤ」と拒否する態度を示すので、大変な時期でもあります。
しかし、その時期が一番子供の成長を感じられて楽しいです。
前職で私は、発達障害のある3歳の子供を担当する事が多かった。
必然的に言動や行動を観察する機会も多かったです。
観察していくと、個人差はありますが、「イヤ」の言動や行動が定型発達の子供と比べて激しい。
ASD(自閉症スペクトラム障害)の子供はこだわりが強くなり始める時期。
こだわりからの「イヤ」というのもあります。
反抗期故なのかこだわりからなのか。
それを見極めるには子供の行動パターンを分析すれば見えてきます。
一番分かりやすいのは、泣いて反抗する時の長さ。
経験上、こだわりの場合は長いです。

この時期は、大人の対応の仕方で子供の成長度合いが変わります。
子供自身がチャレンジをしたいという意味合いが含まれた拒否反応なら一度やらせてみるのが理想。
理想ですが、なかなか難しい。
反抗にイラついて叱りつけて抑えこむ、根負けして子供の言いなりになってしまう保護者もいます。
両方とも良いとは言い難いですが、後者の方はイヤイヤ期が長く続きます。
年長になってもイヤイヤ期?と思うような子供も見かけました。
そのような子供を持つ保護者がよくする行動は、歩くのが嫌で泣くからという理由で抱っこする機会が多い。
それは楽ですが、欲求阻止耐力を子供に上手くつけられません。
長い目で見ると、子供との関係づくりでその後も随分悩むことになります。
幼児期に反抗期がなくて楽でしたというお話も聞きます。
私はそういう話を聞くと、手放しで良かったねとは言えない部分があります。
発達障害の子供の中には、周りを認識する力が弱い事があります。
上手く認識できないために、反抗期がなかったという事も考えられるからです。
小学生の中間反抗期

個人差はあるものの、第二次反抗期は12歳前後から始まります。
しかし、小学2、3年の頃にも反抗的な態度が表れやすく、これは中間反抗期と呼ばれています。
保護者に口答えが多くなるのが特徴。
成長の表れと言えるので、異常というわけではありません。
それよりも危惧すべきことがあります。
小学2、3年頃というのは、発達障害のある子供は色々な問題が浮かび上がる時期です。
・LDの子供なら勉強についていけなくて凹む。
・ADHDの子供はクラスメイトとのトラブルが増加して怒られる。
・ASDの子供は空気が読めない等の理由で嫌われだす。
このような様々なトラブルが起き、心理的な部分に大きく影響を及ぼします。
子供はイライラがつのり、それを発散するために一番身近な母親に当たります。
口答えは勿論のこと、暴言もあります。
それは一見中間反抗期の特徴に似ているので誤解されやすいですが、原因を見ると違います。
中間反抗期と判断して放っておく又は誤った対応をすると、大きくなった時にもっと酷い状態になります。
実際、私はそういう生徒を担当していました。
その生徒は非常に難しい状態でした。
判断を間違えず、早期に相談に来ていればと保護者は悔やんでおられました。
悔やむのは仕方ありませんが、これからどう関わっていくのか?
それが肝心です。
思春期の中学生期

中学生は第二次反抗期がより強くなる時期。
・親から自立したい
・もう大人だという思いが強くなる
・親の言う事一つ一つに反論
・親を突き放すような発言
・親に対して秘密を持つようになる
・親から距離を置くようになる
・親や大人の一方的なルール等に疑問を抱く
こういった態度や行動をとるようになります。
発達障害のある子供も例外ではありませんが、特性によって少し事情が違います。
【ADHDの場合】
ADHDの子供は自分と周りの状況を認識する力があり、突発的に行動してしまう特性があります。
気に入らないルール等があると、反抗的な態度が強く出ることがあります。
実害があるので悩まれるのは当然ですが、全てがマイナスというわけではありません。
違う見方をすると、反抗的な態度が強い自立心へと繋がる可能性があると言えます。
【ASDの場合】
ASDの子供も反抗的態度はとりますが、理由は少し違います。
自分の周りの状況や社会のシステムといった事に対する反発という印象があります。
ただ、私が今まで見てきたASDの子供は、単純に嫌なものは嫌という反発が多かったです。
言葉よりも一貫した態度が重要

反抗期は口答えが多くなるのに、言葉でなんとかしようという方は意外と多い。
しかし、必ずといって良いほど失敗します。
言葉ではなく、態度で示す方が効果的です。
反抗期だから、それに合った態度をとろうと心掛ける親がいます。
それは危うい考えです。
反抗期前も反抗期が終わっても続けて欲しいことがあります。
・少し距離を置いて見守る
・子供の意見を聞く姿勢を常に持つ
反抗期に入ったからといって、突然この2つを実行するというのは難しい。
慣れるのに時間を要します。
常日頃から心掛けて実行していること。
対応もしやすく、自然体で振る舞うことができ、子供にも安心感を与えます。
これにより、反抗期間中の反抗の程度がずいぶん違います。
私は生徒と関わる時は、幼児だろうと中学生だろうと、これら態度を一貫して実行しています。
昔、私のアドバイスを参考にされた保護者がいました。
第一次反抗期はイライラして苦労したそうです。
アドバイスを受けてから、第二次反抗期はそれほどイライラしなかった。
想定してたよりも気が楽だったと仰っていました。
普段から心掛けていた態度が功を奏したようですね。
態度で示すのは簡単なようで難しいですが、慣れると楽です。
ぜひ早い内から実行してみてください。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

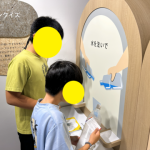










この記事へのコメントはありません。