発達障害者が働くために必要な力~職場以外で身につける方法~
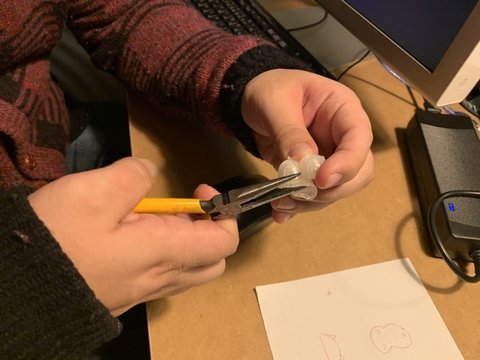
生徒とのバイトでさりげなくサポートをしているひだち教室長の安藤です。
以前は就労支援についてお話しました。
今回は、働くために必要な力についてお話したいと思います。
Contents
社会人基礎力について

経済産業省は社会人基礎力なるものを提唱しています。
「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」という3つの能力。
それを構成する12の能力要素によって成り立っています。
これら3つの能力は確かに大切です。
しかし、発達障害の特性を考えると、難しいものもあります。
前に踏み出す力

・物事に進んで取り組む力
・他人に働きかけ巻き込む力
・目的を設定して確実に行動する力
これら3つの能力要素に分けられます。
物事に進んで取り組むは、発達障害のある人は興味・関心のあるかに左右されます。
興味・関心があれば健常の人以上に強い力を発揮すると思います。
他人に働きかけ巻き込むは、ASDとADHDとでは違いが出てきます。
ASDの人は相手に伝わるように言えるかにかかっています。
ADHDの人(特にHDDタイプ)は勢いがあるので、働きかける力はあるでしょう。
しかし、勢いがありすぎてそれが相手にイラっとさせてしまうこともあります。
目的を設定して確実に行動するは、ASDとADHDとでは原因が違います。
原因は違いますが、計画して行動するのが苦手な事が多いです。
しかし、ASDの人は好きなことや計画の立て方のフォーマットを知っていると出来ることがあります。
ADHDの人は目的を設定するものの色々すっ飛ばしがちですが、結果的には目的を達成することもあります。
それを周りの人が良しとするか良しとしないかで、今後の仕事に対するモチベーションが大きく変わります。
考え抜く力(能力)

・現状を分析し目的や課題を明らかにする力
・課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力
・新しい価値を生み出す力
という3つの能力要素に分解できます。
現状分析は、障害特性よりもその人の能力によると思います。
現状分析が苦手だとしても、誰かと話し合いながらだと出来るというケースもあります。
課題の解決は、経験したことがあるかないかに左右されます。
経験があれば見通しをもてるので比較的問題ない。
発達障害の人は初めての事への対応が難しいので、最初はサポートが必要でしょう。
新しい価値を生み出すは、ADHDのある人は特性上得意分野だと思われます。
ただ、その発想力は意図的に操れるわけではなく、突然閃くことがよくあります。
ASDの人は斜め上な発想をすることがあります。
発想したことを形作れるスキルがあると、大きな強みになるでしょう。
だから、学生の内に何かしらのスキルを獲得するというは大切。
チームで働く力

・自分の意見を分かりやすく伝える力
・相手の意見を丁寧に聞ける力
・意見の違いや立場の違いを理解する力
・自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力
・社会のルールや人との約束を守る力
・ストレスの発生源に対応する力
という6つの能力要素に分けられます。
これらは発達障害のある人にとってはかなりネックな部分。
社会のルールの中には暗黙のルールが存在し、それは教えてもらわなければ理解が難しいです。
全体的に障害特性故に苦手とするものばかりですが、社会のルールを守る力は比較的あると思います。
気になる点としては、ASDの人はルールを守り過ぎる傾向が強いことが多いぐらいかな。
企業が雇用する際に重視する事項

上記のように経済産業省は言っていますが、企業側が求める人材は少し違うようです。
そして、これから書く事項を身につけるためには、どうすれば良いか?
私なりに書きたいと思います。
作業意欲があること

作業意欲は勿論必要ですが、どういった部分でモチベーションを上げるかです。
仕事事態が面白くて意欲が高まるのか、お金が欲しくて意欲が高まるのか。
モチベーションの上げ方は人それぞれ。
ただ、作業意欲を高める前に、仕事をしようという考えを構築する必要があります。
その原動力となるのが「お金が欲しい」という強い思い。
金銭欲を子供の内から持たせることが大切だと私は考えます。

どうすれば良いか、それはお小遣い制にすることです。
一見簡単そうに見えますが、家庭環境によっては難しかったりするようです。
お小遣い制の子供と欲しい時に欲しい分だけ貰える子供とでは、後々の仕事(バイト)に対する意欲が違います。
長年生徒達を見ていて、そう感じます。
また、お金に対する価値観も違うようです。
前者は1万円が高いと実感としてある。
後者は1万円が高い事を知っているが、大した額ではないという認識を持っているケースもあります。
まずは「お金が欲しい」という気持ちを育てる。
そして、働いてお金を稼ぐことが当たり前という認識にすること。
お手伝いという形で、子供の内から出来ることです。
身辺処理ができること
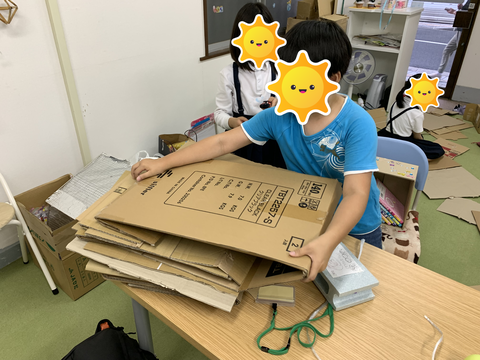
自分の事は自分で出来るというのは当たり前。
そこまで面倒をみる余裕が企業にはありませんので、身辺処理が出来るようにする必要があります。
大人になってから出来るように指導しようとすると、意外と時間と労力が必要。
小さい内から、いかにして身につけさせるかが重要です。
そのためには、幼児の頃から習慣化を図るのが良いです。
服を畳む、掃除機をかけるといったことを一緒にやり続け、成功体験にすると比較的習慣化しやすい。
子供が大きくなればなるほど習慣化は難しくなるので、小さい内からがカギです。
作業の持続性があること

同じ作業を繰り返すのが平気という人は、一体どれぐらいいるのでしょうか?
ASDの人は興味がある仕事ならば続きますが、興味がなければ苦痛でしかありません。
ADHDの人にいたっては、同じ作業を繰り返すのは集中力の持続が難しく、ミスが増えやすい。
持続性を求めるなら、ASDの人には興味を持つ仕事を割り振る。
ADHDの人には刺激(変化)のある作業を任せると持続しやすいです。
子供の内から持続性を求めるトレーニングを行う事は、個人的には反対ですし、あまり意味がないとでしょう。
それよりも、課題や仕事をやりきる力を身につけることの方が重要。
ルールを守ること

ASDの人は基本的にはルールを守ります。
しかし、急に自分ルールを発動することがあり、それがトラブルに発展することがあります。
ソーシャルスキルトレーニング等で、子供の内からルールを守る大切さを教えていきたいところ。
もっとも、本当の意味で大切さを理解するには、ルールを守らなかった時の失敗体験が一番効果的。
失敗体験というのは、子供にとって不都合なことが起きるというもの。
一例として挙げられるのは、ゲームの時間が減る。
子供は痛い目に合うと、ルールに対する意識が高まります。
もっとも、何度もルール違反をするのも子供ではあります。
保護者は根気との戦いになります。
同僚と協力できること
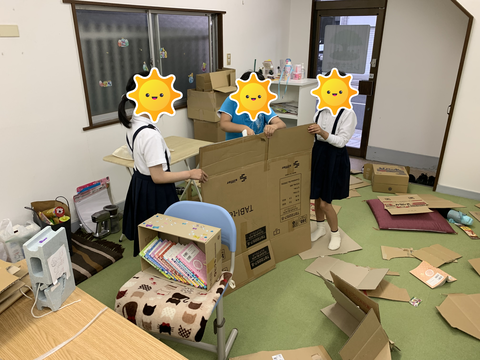
協力し合うことは大切です。
それが出来ないと、戦力として難しくなります。
協力できるかは同僚との共感性で大きく左右されます。
企業には、共感性が高まるような配慮を求めたいところですね。
協力できる人間に育てるには、子供の内から自分をさらけ出せるグループ(例:クラブ・サークル)に所属。
そして、協力しあいながら苦労して目的を達成するという成功体験を積むことが大切です。
職場であいさつや返事ができること

挨拶は基本。
出来る、出来ないとで第一印象がガラっと変わります。
基本中の基本ですが、出来ない人もよく見かけます。
子供が小さい内は、保護者や園(学校)の先生が手本を示す。
ただし、思春期に入るとあまり効果はでません。
子供同士の方が影響を受けやすいので、挨拶ができる子供と一緒に過ごす時間が多いと身につきやすいです。
一番効果的なのは、体育会系のクラブや団体に所属すること。
必ずといって良いほど挨拶を強く求められるので、身につきやすいです。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。


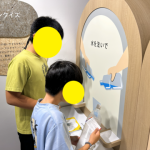









この記事へのコメントはありません。