発達障害者が仕事を続けるためのヒント~ゲーム制作編~

勤めるよりも自分でやった方が良いと思っているひだち教室長の安藤です。
ひだち教室のレッスンの一つに、生徒と一緒にバイトをするというのがあります。
色々な現場で共に働くことで、こういう仕事してたら、生徒はこういう反応をするんだ。
という場面も沢山見てきました。
見聞きした情報から考察

話を聞くだけと実際一緒に働くとでは、やはり印象が異なります。
今回は私が見聞きした情報を踏まえて、下記のことを書こうと思います。
・どんな困難が予想されるか
・どうすれば続けられるかを推測
・生徒の生の声
お子様の将来の参考になると良いなと願っています。
※私の体験談と個人的な見解です。
※私が見た現場の話です。違ったシステムやルールの現場もあると思います。
※ASD、ADHD、LDといっても、タイプは様々なので、全ての人に該当するわけではありません。
ゲーム関係の仕事

守秘義務があるので詳しいことはお話できませんが、ゲーム好きな子供が憧れる仕事です。
ゲーム好きな子供がイメージしているのは、ゲームを作るだけだと思いがち。
現実は違います。
ASDの生徒と共にデバック作業の仕事をしました。
私達がゲームを作るわけではないが、すぐ近くでゲームを作っている人達がいました。
私はその様子をチラチラと見ながら、考察しました。
予想される困難

【ASDの場合】
ASDの人は言葉の取捨選択が苦手なことがあります。
選択が出来ないから、全て自分に投げかけられている言葉と思ってしまい、気疲れしやすい。
逆に、全て自分ではない思ってしまうと何度も注意を受けて自尊心低下に繋がります。
過集中してしまうタイプだと全ての言葉が素通りしてしまう可能性があります。
そのため、誤解が生じてしまうことがあるでしょう。
【ADHDやLDの場合】
聴覚の短気記憶が苦手な人だと、大変苦労すると思います。
長く説明されると聞き取れず、大事な部分も聞き漏らす。
仕事全般に影響を及ぼしかねません。
現場によっては、機密情報漏えい防止のためにメモや携帯を使うことが不可な場合があります。
そうすると、同じことを何度も教育係の方に聞くことになります。
質問は大事だが、あまりにも多いと、教育係の方をイラつかせることに繋がるでしょう。
続けるために必要なこと

専門的な知識を持っているのは最低ライン。
専門知識だけあれば必ずしも続けられるは限りません。
自己理解や環境づくりも必須です。
大まかに、言語性、社会性、環境から考えてみたいと思います。
言語性

【順序立てて説明できる】
仕事の内容によっては、相手に分かりやすく、順序立てて説明する必要性が高い。
同時処理型の人は苦労するかもしれません。
逆に、継次処理型の人にはやりやすいと思います。
【言葉の取捨選択ができる】
専門的な言葉が社内を飛び交っています。
その言葉が自分に投げかけられているのか。
他人に投げかけている言葉なのか。
聞き分ける能力が必要です。
対処法としては、誰に投げかけている言葉か分かるように、最初に名前を必ず言ってもらう。
これが最も手軽に実行しやすい対処方法です。
過集中している人はそもそも聞こえにくい状態。
・直接肩を叩いてもらう
・スマホを机の上に置いておいて呼び出し音やバイブで呼びかけてもらう
こういった対処方法が必要でしょう。
社会性

【挨拶ができる】
社会人としては基本ですが、意外とできない方がいます。
朝礼や帰りの際に挨拶を皆していました。
挨拶をすることに慣れていないと、大きな声で言えなかったりします。
小さい内から習慣づけたいですね。
【「ありがとう」を言う】
些細なことでも感謝の言葉を述べることは、集団で仕事をする上で必要なことです。
仲良くなることは勿論、手伝ってもらったり、教えてもらいやすくなります。
これも小さい内から習慣づけるべきスキルですね。
【自分が出来ること、出来ないことを理解している】
広義の意味での社会性なので、自己理解も含めました。
仕事場では、出来る事出来ないことを理解した上でやっています。
その中でお互いを補完しあっていました。
【出来ないことを断れる】
出来ないことは出来ないとハッキリ言う。
自分の首を絞めずにいられます。
実際、出来ないことは断っている場面をよく見かけました。
【分からないことを自ら聞ける】
聞きに行かず、知ったかぶりをしたばかりに、後で注意を受けていた人がいました。
聞くは一時の恥だが、聞かぬは一生の恥ということわざがあります。
この仕事はまさにその通りだと実感します。
【相手に確認する】
発達障害のある人は、聞き間違いや思い込みというのが比較的多いです。
それはトレーニングでどうこうするには限界があります。
自分はそういうタイプだと、まずは受け入れること。
その上で、伝えてきた相手に確認することを習慣化する。
これだけで、だいぶミスは減ります。
【多角的に物事を考える】
この業界に何年もいる方に聞きました。
多角的に物事を考えられることはこの業界では非常に重要とのこと。
世の中には色々なタイプのゲーマーが存在し、ゲームのプレイ方法も千差万別です。
このゲーマーはどういう思考からこういう行動にいたったのか?
多角的に、客観的に考えられると、随分仕事に役立ちます。
一見関係なさそうなプログラミングも例外ではなく、なくてはならない能力とのこと。
プログラミングは論理的思考が必要だからだそうです。
多角的に物事を考えるというのは、一朝一夕に身に着くものではありません。
・自分の価値観とは違う価値観に触れること
・外で色々な体験をすることが重要
私を担当したリーダーは、そのように仰っていました。
ひだち教室としての方向性が間違っていなくて嬉しかったです。
【時事ネタを知っている】
仕事を続けるには、人とのコミュニケーションは重要。
仕事上のコミュニケーションは勿論のこと、仕事以外のコミュニケーションも大切です。
コミュニケーションをとるためには、会話のネタとなる情報が必要です。
ニュース等から世の中の事を知っておくと、会話が成立しやすくなります。
【相手が関心を持っていることに関心を持つ】
相手が関心を持っていることに関心を持つと、会話が弾み、仲良くなりやすい。
ゲーム業界の人はゲームに関心を持っています。
でも、どういうゲームを特に関心を持っているかは、人それぞれ。
その人がどういうゲームに関心を持っているかを聞く。
そして、それについて質問すると仲が良くなりやすいです。
ASDの人はそういう部分が苦手だったりします。
苦手だけど、全く関心を持てないわけではありません。
関心を持つことのメリットを成功体験としてあると出来ます。
ソーシャルスキルトレーニング等で獲得したいですね。
環境
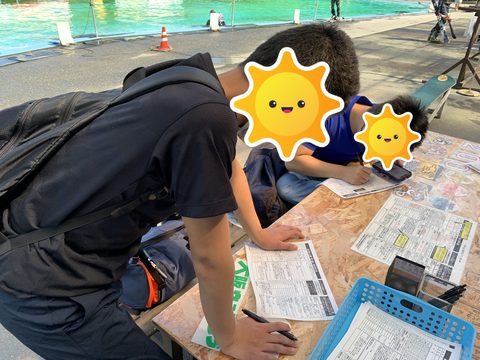
【長時間パソコンを見続けられるための工夫】
ゲーム作りは、長時間パソコンを見続けます。
長時間見続けると眼精疲労だけでなく、精神的疲労もたまってきます。
自分にあった疲労が蓄積しにくい方法を見いだすか、誰かの真似をしてみるのも一つの手。
長い文章がズラズラと書かれたメールやチャット等のやり取りが多いです。
長い文章を読むという行為に慣れておくことも必要ですね。
LDがある人の中には、文章を見ると文章が歪んで見えたりする人もいます。
文章の読み上げ機能があると良いかもしれません。
そういった機能を会社に取り付けてもらえないか、頼んでみても良いと思います。
【役割を明確化する】
ASDの人は急な変更がとてもしんどい。
パニック状態になる人もいます。
ただ、急な変更は頻繁に起きます。
一緒にデバック作業のバイトをしたASDの生徒曰く。
「急な変更が頻発し、変更が起きる度に強いストレスを感じ、とても疲れた」
とのことでした。
役割を明確化し、それに没頭できる環境を作るのが会社の役目だと思います。
没頭できた時、発達障害のある人の力は凄いですよ。
【興味があること、得意な仕事を振ってもらう】
ゲーム関係の仕事は役割が細分化されているようです。
どういう役割を与えられるかは、続ける上で非常に重要。
発達障害のある人は興味があることならどこまでも頑張れる傾向があります。
就職するまでに、自分の得意分野を確立することが重要です。
生徒のデバック作業の感想

【A君の体験談と感想】
作業自体はマイペースに出来た。
分からないことは質問を何度も出来たので問題はなかった。
同じグループの方同士で作業に関することでモメ始めたのは怖かった。
こんなにもめることがあるとは思っていなかったので衝撃を受けた。
その影響でグループ内で嫌な雰囲気になり、質問をしに行くと邪険にされることがあった。
とても気を遣うことになってしんどかった。
トラウマになった。
1回目は良い印象を持たれやすいが、2回目、3回目となると怖い。
何故なら、作業を出来ることが当たり前と思われだすので不安が強まる。
作業自体は出来るので、次回は少し時間を空けてからやってみようと思う。
【B君の体験談と感想】
知らないゲームだったので、そのゲーム固有の名称等を覚えるのが大変だった。
長時間画面を見ていたので、目がとても疲れた。
狭い空間に長くいるのは少ししんどかった。
作業自体はマイペースでできたのはありがたかった。
座っての作業は楽で、体力的に余裕があった。
指導者は親切に丁寧に教えてくれたので、全体的にとても良い印象を持った。
またやってみたいと思う。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。












この記事へのコメントはありません。