大江山の鬼嶽稲荷神社【京都府福知山市大江町北原】

鬼にまつわる所に行くとワクワクするひだち教室長の安藤です。
日本の鬼の交流博物館周辺には、鬼にまつわるスポットがいくつかあります。
福知山市の観光マップを見ていると、鬼と関係の深そうな神社を発見。
それが鬼嶽稲荷神社。
結論から言いますと、神社が鬼と直接関係があるというわけではありません。
しかし、大江山周辺は鬼の伝説がある地であり、神社の近くには鬼にまつわるスポットもありました。
お鬼嶽稲荷神社情報

神社までの道のりは長く、車がないと行くことは難しい。
鬼の交流博物館から車を走らせていると、酒呑童子の里のグラウンドに通ずるゲートがあります。
ゲートのすぐ隣には、赤鬼、青鬼がお出迎え。
私達はそんなゲートの脇にある道を進みました。

川に沿って山奥に進んでいると、ログカフェの案内板を見かけました。
こんな所にカフェ?と、正直驚きました。
案内板を見かけてから10分ほどでログカフェを発見。
ポルトガル語で森林という意味のFLORESTAという名の店。
オシャレ感があり、季節が良ければ気持ちよく過ごせるでしょう。
しかし、今は冬。
残念ながら店も閉まっていました。

フローレスタの看板は手作り感があります。
看板の横に立っている龍も手作り感満載。
この手作り感が好印象ですね。
雲海スポットとして有名な大江山

一体どこまで続くのか、不安になりながらさらに奥へと進むと、ようやく到着。
しかし、神社のすぐ近くには駐車場はありませんでした。
そのため少し戻ることに。

神社から徒歩5分ほど離れた所に駐車場があります。
落下防止の柵もなく、線も引かれていない。
駐車場というより、単なるスペースという感じ。

大江山はブナの原生林で多様な虫や鳥が生息しており、野生の宝庫。
それ故登山者が多く、神社の隣には大江山休憩所がつくられていました。
10月~12月の早朝に寒暖差が大きくなると雲海が発生し、幻想的な光景を見ることができます。

鬼嶽稲荷神社は雲海が発生する方角に向けて視界が大きく開けています。
雲海鑑賞をするには絶好のポイント。
一度は見てみたいですね。
そんな自然に囲まれた大江山ですが、冬に訪れる人は少なく、私達以外は誰もいませんでした。
鬼嶽稲荷神社と周辺スポット


鬼獄稲荷神社の本殿。
社伝によると、四道将軍の丹波道主命がこの地にやってきました。
そして、父である日子坐王の旧蹟に神祠を建立したと伝えています。
以前は頂上付近に本殿がありましたが、十九世紀中ごろに現在の場所に移されました。
同時期に、伏見稲荷大社の宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)を勧請。
御嶽から今の鬼嶽稲荷神社と名を改めました。
この地方の主産業であった養蚕の神、稲作の神として、農民たちに崇拝を受けていました。
勿論現在も崇拝を受けています。

農民たちに崇拝を受けていたからか、本殿を守るお稲荷さんは威厳のある感じはない。
親しみやすい表情をしています。
また、尻尾が太くて特徴のあるお稲荷さんですね。
御朱印をもらおうとしたのですが、冬のため社務所は開いておらず、手に入れることはできませんでした。

神社から少し下ったところに鬼の洞窟があります。
道幅が狭くて急な坂道な上、雨でぬかるんでいたので、安全をとって行きませんでした。
ぬかるんでいなければ必ず訪れたい所です。

帰りに気になる看板を見かけました。
不動の滝、ぶな林といったものにはたいして興味を持ちませんでした。
しかし、「金時の逆さ杉」には興味を持ちました。
大江山には最強の鬼とうたわれる酒呑童子の住処があります。
そして、酒呑童子と源頼光達との闘いの地でもあります。
源頼光達の中に金太郎で有名な坂田金時がいます。
坂田金時は崖を渡れなくて困った時に、金時が巨大な杉を引き抜いて橋にしたそうです。
そんな伝説の杉を見ないわけにはいきません。

簡単に見られると思っていたのですが、杉がある所は道なき道を進み、急斜面を登った先にあります。
前日からの雨で地面が思った以上にぬかるんでいて、足を滑らせて落ちる危険性が高かったので諦めました。
生徒を危険な目に合わせるわけにはいきませんので。
鬼嶽稲荷神社を参拝する方は、私達みたいに冬に訪れるのではなく、暖かくて晴天の時に参拝してください。
もっと楽しめると思います。
アクセスと地図
北近畿丹後鉄道:大江駅から車で35分。
駐車場:あり。ただし、数台しか駐車できません。駐車する時は気を付けてください。
拝観時間:自由。
定休日:なし。
御朱印:御朱印は書置き式で、直書きはできません。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

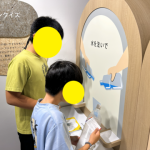










この記事へのコメントはありません。