発達障害児にチャレンジさせる方法を伝授!

成長するにはチャレンジ(挑戦)することが大事だと信じているひだち教室長の安藤です。
新しいことへのチャレンジは人としてグッと成長します。
しかし、発達障害のある人は特性やこれまでの経験からチャレンジすることに消極的なケースが多いです。
ひだち教室に通う生徒達も、最初からチャレンジする姿勢を示しているのは稀です。
今回は下記の内容でお話ししたいと思います。
・ひだち教室がチャレンジで大切にしていること
・チャレンジするのが消極的な理由
・チャレンジさせる方法
「チャレンジさせる」とは、子供に強制させるのかと思われる人もいるでしょう。
それは否定しません。
しかし、最初は強制だとしても、成功体験に結び付けば自己肯定感や自尊心が高まります。
また、経験すれば世界観が広がり、行動の範囲が広がります。
新しい価値観が構築されることもあります。
実際私はそういった成長を示す生徒達を目の当たりにしてきました。
だから私は、これからも信念を持って生徒達にチャレンジする機会を与え続けます。
Contents
ひだち教室がチャレンジで大切にしていること

ひだち教室は体験を重視した塾。
そのため、必然的に生徒達にチャレンジしてもらう機会は多いです。
生徒に新しい事や苦手な事にチャレンジしてもらいますが、そればかりだと辛い。
生徒達にチャレンジしてもらうにあたって、私は大切にしていることがあります。
・信頼関係の強さ
・チャレンジできるかの心理状態の見極め
・好きな事や出来ることだけをする活動をたまに取り入れる
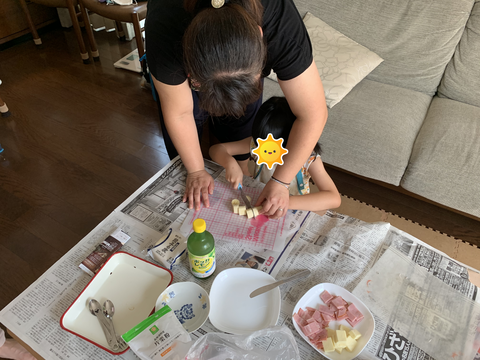
信頼関係が構築されないと、全てにおいて上手くいきません。
信頼関係の構築方法は生徒によって違うので「こうしましょう!」とは一概には言えません。
一つ言えるのは、子供にとって意外性のある何かをすると構築できたという手応えを感じられます。
その何かは、言葉であり、態度であり、行動だったりします。

チャレンジできるかの心理状態の見極めは大切。
勉強や人間関係、日々の生活で生徒達の心は消耗しています。
中には心が挫かれる事もあります。
そうなると、心のエネルギーが枯渇してしまい、何かにチャレンジできなくなります。
そういう時、私は生徒にチャレンジを求めません。
まずは出来る事や好きな事をしてもらって、心のエネルギーを溜める事に専念してもらいます。

好きな事や出来ることだけをする活動はたまには必要。
毎回チャレンジする活動となると、生徒達はウンザリします。
息抜きの意味合いの強い活動を取り入れることで、次の活動の活力にもなります。
チャレンジするのが消極的な理由

発達障害のある子供は新しい事にチャレンジしようという思いがわきにくいです。
ADHD(注意欠如・多動性障害)の子供は特性的にチャレンジすることは好き。
しかし、失敗体験を積み重ね過ぎると失敗を恐れるようになります。
失敗を恐れると自己防衛反応が強くなり、チャレンジする意欲がわかなくなるのです。
幼児期よりも小学校に入ってからの方が顕著に表れます。

ASD(自閉症スペクトラム障害)の子供は初めての事、知らない事に不安を持ちやすい。
楽しみよりも不安が頭の中を支配し、大きな拒絶反応を示す子供もいます。
ただし、体験してしまえば平気になるケースは多いです。
子供にチャレンジさせる方法

発達障害のある子供に何かチャレンジさせたいと思う親や指導者は多いと思います。
発達障害の特性故の難しさに、頭を抱えていることでしょう。
しかし、特性があってもチャレンジさせることはできます。
それは長年私は実践してきたので確信があります。
強固な信頼関係が心の支柱になる

指導や支援する時は信頼関係の構築は当たり前。
『この人は良い人』『この人は優しい』『甘えられる人』
指導者が心の支柱になるには、この程度の信頼関係では足りません。
『この人が言うなら出来る』『安心感を持てる』『尊敬できる』
心の支柱になるには、これぐらい強固な信頼関係が必要です。
強い信頼関係を構築するのは大変ですが、上手く信頼関係を構築できたら後は楽。
何かにチャレンジしてみようと誘うと、意外とあっさりとOKが出るようになります。
こんな事例があります。
当教室に通うある生徒は、なかなかバイトをしようとしませんでした。
不安が強すぎるためです。
ところが、私と一緒に登録バイトをしようと言うと、OKが出ました。
このように、心の支柱となっている人がいることで、一歩を踏み出すことが出来るのです。
子供が理解しやすい指導

やり方が分からない状態でチャレンジさせられるというのは理不尽極まりない。
「やったら出来るようになるから!」
なんて事を保護者や先生は言ってませんか?
出来るという確信があれば良いです。
確信がないのに言うのは、子供の心を挫くことに繋がるのでNG。
子供はできるようになりたいと思っているが、出来ないのです。
だから、その子が理解しやすい言葉を使ったりして教える必要があります。
それがマッチすれば出来るようになり、チャレンジする意欲もわいてきます。
あえて自由にさせる

こだわりの強いタイプ(自己流でやりたがる)なら、あえて自由にさせるのも一つの手。
自由にさせることで、子供なりに創意工夫を始めます。
成功と失敗、どちらの結果になっても良いです。
大切なのは、チャレンジした事を褒めること。
すると、またチャレンジしようという意識が強くなります。
勇気づけ

発達障害のある子供は自己評価が低いことが多いです。
「自分にはできない」「自分には無理」
といった事を言う子供もいます。
しかし、出来るという確信があるなら「○○ちゃんなら出来る」のように励まします。
言葉がけで勇気づくならそれでOK。
出来る力があるのに、子供自身が無理と判断して逃げ出そうとする場合もあります。
そういう時は、指導者は毅然とした態度をとります。
「○○ちゃんなら出来る。だからやってみよう」「不安ならサポートするから大丈夫」
といった感じで言葉をかけ、やらせます。
最初は怖がるかもしれませんが、「出来た!」という経験を積めたら問題ありません。
チャレンジ精神がわくようになり、自ら何度もやるようになります。
視覚的に提示する

ASD(自閉症スペクトラム障害)の特性にイメージ力の低さが挙げられます。
そこで、画像や動画といった視覚的支援物を使います。
見通しを持てるので安心でき、チャレンジしてみようと思えることもあります。
ただし、活動内容によっては逆に不安が増長するケースもあるので注意が必要です。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。












この記事へのコメントはありません。