発達障害の子供に自己決定力を~自己決定力が育まれにくい環境~

自己決定力は生きる上で必須と思っているひだち教室長の安藤です。
以前ある新聞に、明石洋子さんによる発達障害についての記事が掲載されました。
そこには「自己決定する力」という実に興味深い記事でした。
そこで、今回は自己決定力について触れたいと思います。
発達障害のある子供をどう育てるか

明石洋子さんが自らの体験を踏まえ、発達障害の子供を育てている人を応援されています。
応援の一つとして「思いを育てる、自立を助ける」という本を出されました。
子供を育てるにあたり、重要なキーワードとして「自己決定する力」が挙げられていました。
これはひだち教室の目標にも掲げており、共感しました。
記事には、自己決定できるようにするために選択肢を設け、選んでもらうことを繰り返した。
そうすることで本人の「思い」を育ててきたことで、自ら目標を設定できるようになった。
記事にはそのように書かれていました。
まさに私が目指す道です。
自己決定力が育ちにくい環境

自己決定なんて簡単に出来る。
そのように思われる方は結構います。
実はそう簡単なことでもありません。
周りの人間の関わり方や環境によっては、歳を重ねていく内に難しくなるケースもあります。
私がよく見聞きする原因を紹介します。
保護者が先に決めてしまう

発達障害の子供を持つ保護者ほど、先に決めてしまうケースが多い。
それは何故か?
・行動に移すまでに時間を要することがよくある
・手先が不器用過ぎて失敗する場面をよく見てきている
・失敗してからのフォローの方が大変
・保護者が決めた方が早く終わる
これらの理由で、保護者が何でも決めてしまう。
必然的に子供は自己決定する経験が減り、自己決定を出来なくなります。
そうなると、肝心な時に決めて欲しくても、子供は「なんでもいい」と言うようになります。
拒否され続ける

小さい内は自分で何でも決定していたが、小学生になってからは出来なくなったという話をよく聞きます。
集団生活では、自分が決定しても拒否されることがよくあるからです。
その頻度が多過ぎると心がくじかれる。
その結果、自己決定することが怖くなり、自己決定することができなくなります。
これは小学生の時に起きるとは限りません。
もっと年齢を重ねてから起きることもあります。
実際、こんな生徒がいました。
高校時代にクラブを頑張り、責任ある立場となって自己決定をしまくった。
しかし、周りの人達に拒否され続けた。
それにより、その生徒はこのように思うようになりました。
「自分は決定しない方が良い」
「拒否されるのが怖い」
従順な子供の危うさ

発達障害の子供は特性故の行動や言動により、定型の子供よりも怒られる頻度は多い。
そのため、子供は二極化していきます。
とことん反発するか、従順になるか。
反発するということは、問題もありますが、自己決定する力と言う観点ではOKです。
しかし、従順のタイプは危うい。
親に言われた通りにすれば良い、無駄に怒られないからこれで良いという思考に陥る。
そういった思考は、自己決定力を消失させるだけではありません。
・問題解決能力の欠如
・自己肯定感の低下
・他者責任思考
・親への依存が強まる
このようなことが起こりえ、自立からほど遠くなってしまいます。
自己決定する力は環境によって、とても左右されます。
自己決定できるようになったと思ったら、何かが原因で出来なくなることもあります。
自己決定を出来るようになることは大切。
同時に維持することも大切だと、私は多くの生徒達を見てきて、つくづく思います。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。


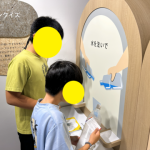









この記事へのコメントはありません。