子育てや自立をサポートするひだち教室~動ける教室とは?~

生徒のためなら頑張れるひだち教室長の安藤です。
ひだち教室のコンセプトは『動ける教室』。
おそらく多くの人は「?」が頭に浮かぶと思います。
そんな「?」が「なるほど!」に変わるよう、ひだち教室についてお話しします。
ひだち教室の特徴

『動ける教室』の所以は4つあります。
・外での体験活動の重視
・実践型の就労支援
・緊急時の対応
・講演会や研修会の実施
積極的に外に出て動く(活動する)という意味。
そして、公的な機関では動きづらい事案でもひだち教室は動ける。
そういった意味合いが含まれています。
外での体験活動の重視

私は『座学よりも体験の方がより多くを学べる』という考え。
そのため、体験活動を重視しています。
その考えを具現化しているのが、生徒と保護者から大好評の課外活動です。
行く場所や内容は様々なので、生徒達は同年代の子供達よりも経験が豊富だと思います。
外で活動をするからには、「体験して楽しかった」で終わらせては意味がありません。
ねらいや目標を設定して活動をしています。
・ライフスキルやソーシャルスキルを身に着ける
・コミュニケーションの取り方を学ぶ
・情報を受け取るポイントを学ぶ
・多種多様な技術・知識を持った人達と出会うことで新しい世界を知る
・自信をつける
・思考や行動を起こすための選択肢を増やす
上記以外にもねらいはあり、生徒によっては個別の目標を設定することもあります。
生徒達は活動中に様々な表情、言動、行動を見せてくれます。
そんな様子を保護者はビデオで見ることが出来、我が子の意外な姿を見て驚きます。
また、継続して活動に参加することで変化も感じられるようになります。
・暗かった表情が明るくなった
・色んなことに興味・関心を持つようになった
・子供の価値観が変わった
・自信がついた
・問題行動(例:列に並べるようになった)が減った
といった保護者の声をよく聞きます。
体験活動は子供を成長させる・変化するキッカケになるので、ひだち教室では欠かせません。
実践型の就労支援

大人の生徒もいるので、仕事に関しても考えていく必要があります。
生徒には理論よりも実践から多くのことを学んで欲しいと私は思っています。
しかし、バイトをする勇気を持てない生徒もいます。
そこで、生徒と一緒に登録バイト(6~8時間労働)をします。
同じ目線で、同じ仕事、同じ人達と関わり、生徒とツーカーの会話が成立しやすい状況にした上で、
・何が出来て、何が出来なかったか
・どういう人がいて、どういう人が苦手か
・どういうアドバイスがあったら良いか
といった事を、バイト後にご飯を食べながら聞くようにしています。
バイト経験をもとに、将来に向けての話し合い(自己理解を深める)もします。
・自分にはどういう仕事が向いているのか
・どういう雰囲気の職場が合っているのか
・どういう自助能力をつけていけば良いのか
公的機関では行えない支援方法ということもあり、保護者からの要望が多いです。
生徒と一緒に行ったアルバイトの記事を掲載していますので、そちらも一読頂ければと思います。
>>>発達障害者への就労支援
緊急時の対応
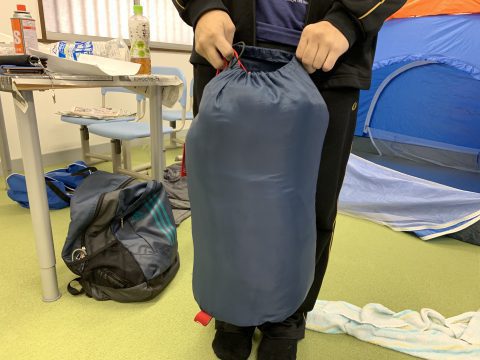
発達障害のある人達と関わっていると、緊急を要する事態というのはあります。
これまでの経験上、すぐ動いて対応することは生徒のその後の人生に大きく関わってきます。
私は可能な限りすぐ動くように心がけています。
過去にこんなことがありました。
ある日のこと、鬱と診断されている生徒(大学生)は明らかにしんどそうな表情をしていました。
生徒は日常生活や学校生活で様々なプレッシャーを感じ続けている。
それを処理しきれなくなったのが原因でした。
鬱の程度が重くなっていて、すぐに手を打たなければ最悪のケースも考えられる。
私はこの生徒には現実のプレッシャーを忘れられる環境がすぐに必要と判断。
急きょ二泊三日の旅を一緒にすることにしました。
この旅が生徒の状態が良い方向に向かい始めるキッカケになりました。
現在は就職もしており、冗談を言えるほどになっています。
もしあの時すぐに動かなかったらどうなっていたか・・・。
考えただけでもゾッとします。
講演会や研修会の実施

私は発達障害関連の啓蒙活動を積極的に行っています。
講演会や研修会などに講師として依頼されることもあれば、ひだち教室主催で開催することもあります。
過去には下記のような場で講演会等をさせて頂いたことがあります。
・草津市にある子育て関係のNPO団体主催の講演会
・滋賀県内の高校の校内研修会
・支援センター職員による就労支援講演会(ひだち教室主催)
・滋賀県で放送されているラジオに出演
・大津市の保育所で園内研修会
特殊な場としては、バイト中に急遽現場のスタッフ相手にしたこともあります。
私が講演をする時は一般的に言われていることはあまり話しません。
むしろ、発達障害者の中にはこういう人もいるんだという事例を話すようにしています。
事例を聞いて共感する人もいますが、むしろ「まじか!?」と驚く人の割合が多いです。
私はあまり他では聞かないような事例を持っていて、そんな事例を多くの方に知って欲しいと思っています。
それが多様な関わり方をするための第一歩だと信じているから。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。












この記事へのコメントはありません。